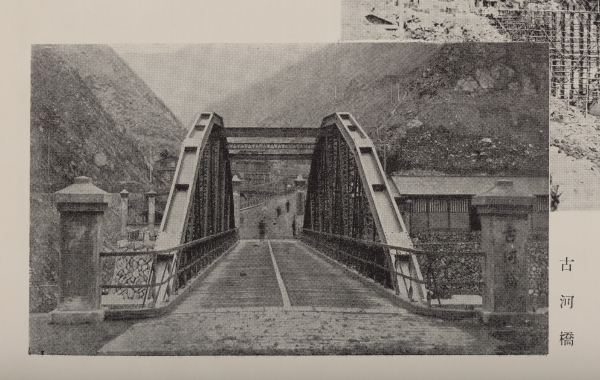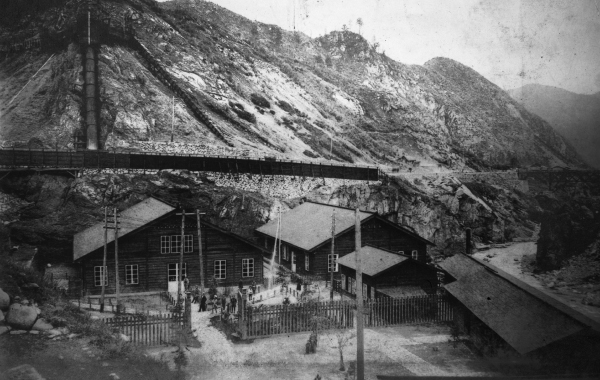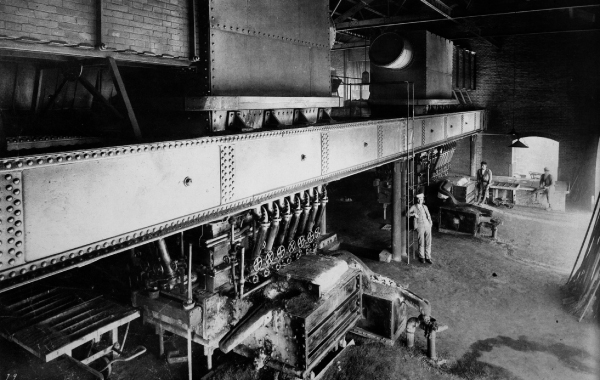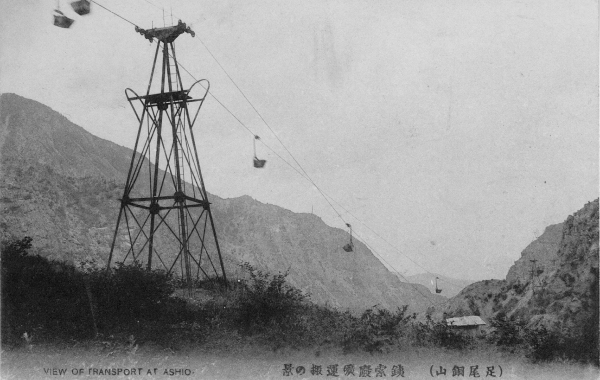足尾銅山とは
足尾銅山とは、足尾町の中心に位置する「備前鍎山」のことです。足尾町には、多くの山々が連なっていますが、銅を含む鉱石はこの山でしか採れません。鉱石を求めた坑夫たちによって、山体の内部には、高低差1,000mの範囲に総延長距離1,234kmにも及ぶ坑道が掘り進められまし た。
足尾銅山の歩み
| 年号 | 出来事 |
|---|---|
| 1877 (明治10)年 |
古河市兵衛が足尾銅山を買収する。 |
| 1881 (明治14)年 |
鷹之巣坑で神保の直利を補捉、足尾銅山好転に向かう。 |
| 1883 (明治16)年 |
足尾産銅量が発展、日本一となる。 直利橋製錬分局、本山病院、東京・本所熔銅所をそれぞれ創設、足尾町内の道路大改修を開始する。 |
| 1884 (明治17)年 |
本口坑開坑で横間歩大直利を補捉、足尾銅山の銅生産量が日本一となる。 |
| 1885 (明治18)年 |
通洞坑開鑿開始。 |
| 1886 (明治19)年 |
民間初の銅山私設電話を開設 |
| 1887 (明治20)年 |
松木村で大規模山火事発生。 |
| 1890 (明治23)年 |
渡良瀬川の大洪水で鉱害の被害が拡大する。 |
| 1896 (明治29)年 |
通洞坑完成。 |
| 1897 (明治30)年 |
銅山周辺の山で植林が始まり、現在も継続中である。 |
| 1897 (明治30)年 |
東京鉱山監督署長、足尾銅山に鉱毒除防工事命令。 |
| 1901 (明治34)年 |
田中正造が衆議院議員を辞職。 明治天皇に直訴状を提出しようとして遮られる。 |
| 1902 (明治35)年 |
足尾台風直撃。 |
| 1903 (明治36)年 |
古河市兵衛死去、養子の古河潤吉(実父陸奥宗光)が足尾銅山の経営を担う。 |
| 1906 (明治39)年 |
谷中村が廃村。日光精銅所操業開始。 |
| 1907 (明治40)年 |
足尾暴動事件発生。銅山施設の大部分が焼失。 |
| 1912 (明治45)年 |
足尾鉄道(桐生駅 – 間藤駅間、現在のわたらせ渓谷鐵道)開通。 |
| 1956 (昭和31)年 |
古河オートクンプ式自溶製錬設備が完成し、亜硫酸ガス対策が完了する。 |
足尾銅山4大工事